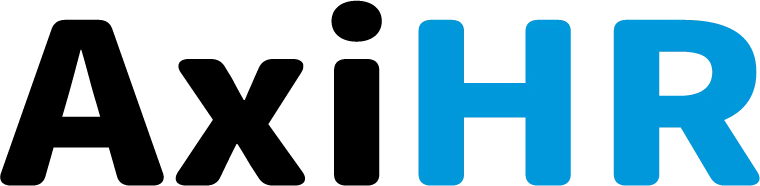内定後の競業誓約書にサインする前に確認すべきこと5選
2025/10/20
―“契約書サイン=入社決定”ではありません。
こんにちは!不動産専門の転職支援サービス「キャリすぐ」を運営するAXIDEA編集部です。
内定をもらって安心したのも束の間、
「入社前に競業誓約書への署名をお願いします」
と企業から提示されるケースがあります。
一見すると“形式的な書類”に見えますが、内容によってはあなたの転職や将来のキャリアに制限をかける重大な契約です。
特に不動産業界では、顧客情報や契約ノウハウなど守秘性の高い情報を扱うため、競業誓約書(=競業避止契約書)の提出を求められることが珍しくありません。
この記事では、サインする前に必ず確認すべきポイントを具体的に解説します。
LINEで相談そもそも「競業誓約書」とは?
競業誓約書とは、入社後または退職後に、会社と競合する事業に関わらないことを約束する契約書です。
目的は主に次の3つ。
- 企業の営業秘密や顧客情報の保護
- 公正な競争環境の維持
- 退職者によるノウハウ流出の防止
法律上は「職業選択の自由(憲法22条)」とのバランスが必要で、制約が過度な場合は無効と判断されることもあります。
関連記事:競業避止義務に抵触しないか?
サイン前に必ず確認すべき5つの項目
① 競業の「対象範囲」が明確か?
最も重要なのは、「何をもって競業とするか」の定義です。
曖昧な表現(例:「同業種への転職を禁止」「当社と同種の事業に関与しない」)だと、実際の転職時に判断トラブルが起きやすくなります。
確認ポイントは以下の3つです。
- 対象となる業種・職種は具体的に記載されているか
- 「関連事業」など曖昧な言葉で広く制限されていないか
- 自社と無関係な分野(例:住宅販売と不動産テック)が含まれていないか
② 制限される「期間」が合理的か?
通常、競業避止期間は退職後6か月〜2年以内が一般的です。
3年以上の制限は過度と判断されることが多く、補償がない場合は無効とされる傾向があります。
確認ポイントは以下の3つです。
- 期間が明記されているか(無期限はNG)
- 「退職後〇年間」と明確に書かれているか
- 期間中の補償金・手当の記載があるか
③ 競業地域(エリア)が限定されているか?
地域の範囲が全国に及ぶような契約は、過度な制約として無効になる可能性があります。
確認ポイントは以下の2つです。
- 「東京都内」「関東圏」など、明確な範囲になっているか
- 実際の営業エリアと一致しているか(例:東京勤務なら関西圏は関係ない)
④ 守秘義務条項との“境界線”が明確か?
競業誓約書には、守秘義務条項がセットで入っていることが多いです。
ただし「何を守秘情報とするか」が不明確だと、普通の業務知識まで制限されてしまう恐れがあります。
確認ポイントは以下の2つです。
- 顧客名簿・契約書類・価格表など具体的な項目が挙げられているか
- 自身の営業スキルやノウハウまで制限対象になっていないか
⑤ 補償・違約金条項があるか?
競業避止を強制するなら、企業は相応の補償を行うのが原則です。
確認ポイントは以下の2つです。
- 退職金や特別手当など、金銭的補償があるか
- 違反時の「損害賠償額」や「違約金」が不当に高く設定されていないか
無補償で一方的に制約を課す契約は、無効の可能性が高いです。
不動産業界特有の注意点
不動産業界は、顧客・オーナー情報や物件データなどの営業秘密が多く、競業誓約書の範囲が広く設定されがちです。
特に以下のようなケースは要注意です。
- 元の勤務先と同じエリアで仲介・管理業を行う
- 同一顧客への再アプローチを行う
- 独立後に元勤務先の仕入れ情報を利用する
これらは不正競争防止法(第2条1項7号)に抵触する可能性もあるため、「競業誓約書=形式文書」と軽く扱うのは危険です。
サインを求められたときの対応手順
- その場で即サインしない
→ 一度持ち帰り、内容を冷静に精査する。 - 疑問点をリストアップする
→ 期間・地域・補償・定義を中心に確認。 - 転職エージェントや専門家に相談する
→ 法的観点からアドバイスを受ける。
関連記事:円満退社のための引継ぎ計画は?
サイン後にトラブルを防ぐためのポイント
- 契約書のコピーを必ず保管する
- メール・口頭のやり取りも記録しておく
- 転職後は「元顧客・取引先との接触」を避ける
- SNSでの発信内容にも注意する(顧客名・事例の記載など)
もし退職後に競業制限の指摘を受けた場合でも、「誠実な対応+文書記録」があればトラブルを最小化できます。
まとめ:署名は“儀式”ではなく“契約”である
- 競業誓約書は、あなたの将来に影響を与える法的契約
- 期間・地域・補償が合理的であるかを必ず確認
- 曖昧な場合は、サインせず相談する勇気を持つ
「安心して働くための書類」が「足かせ」にならないように契約内容を理解したうえで、納得してサインするのが大切です。
LINEで相談